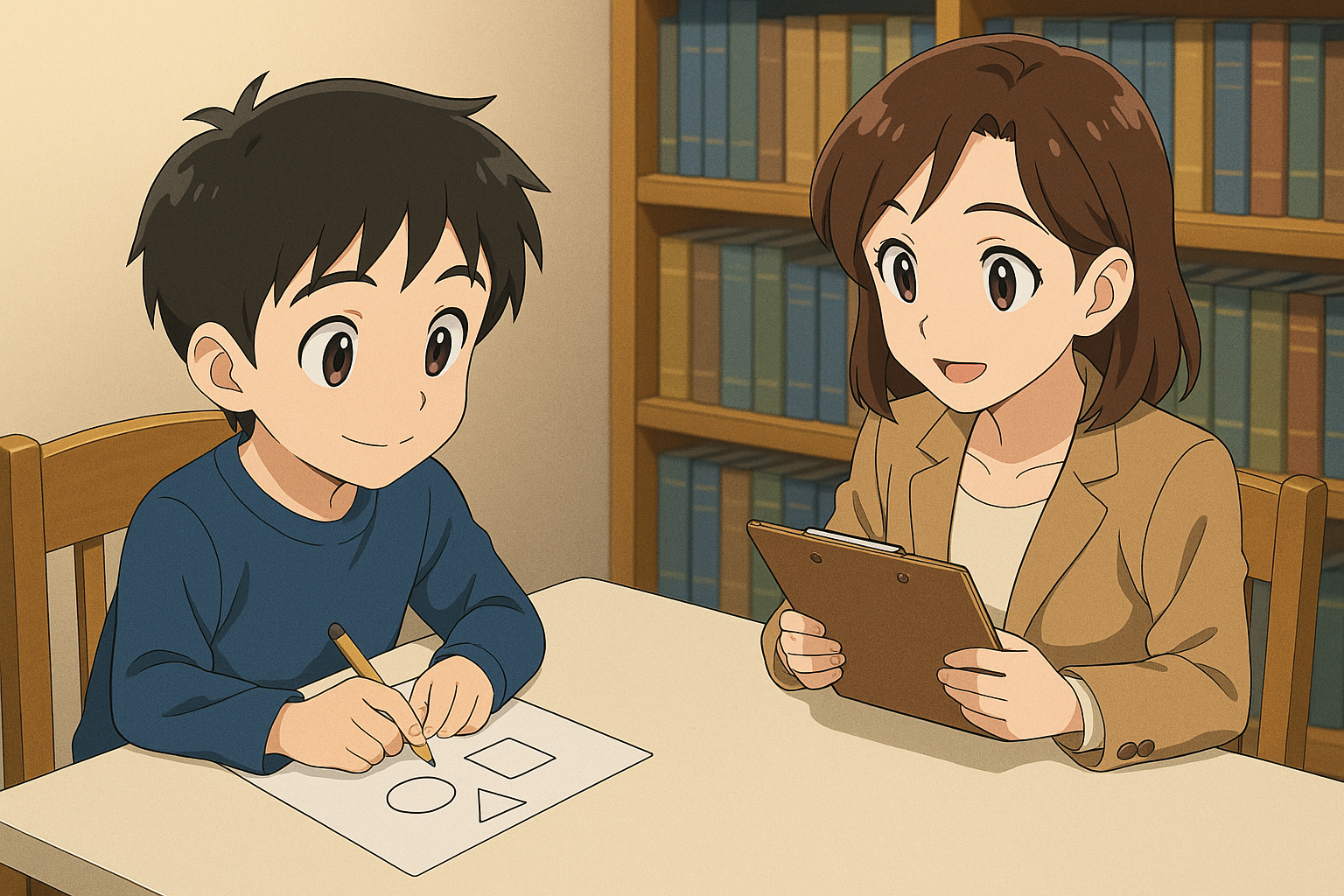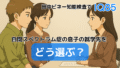「うちの子、小学校どうなるんだろう?」
自閉症の診断を受けた息子、きー君(6歳)
年長さんになり、進学先のことを真剣に考える時期になりました。
就学相談の案内を受けたものの…
「どんなことをするの?」
「特別支援学校?近所の小学校?」
「近所の小学校に通うとしたら、普通級と支援級、どう決めればいいの?」
と分からないことばかりで不安でいっぱいでした。
この記事では、実際に私たちが受けている就学相談の流れや、「田中ビネー知能検査」の体験談、そして親として感じたことを正直に綴っています。
同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

我が子の小学校入学について考える時期になり、不安…。
就学相談ってどんなことをするんだろう?
このようなお悩みに対して、この記事では以下のことがわかります。
・就学相談とは何か
・就学相談はどんなことをするのか
・田中ビネー知能検査を受けた当日の流れや様子

自閉スペクトラム症の6歳の息子(きー君)と、今のところ定型発達であろう3歳の娘(あーちゃん)を育てています!
障害児育児は6年目。15年間小学校教諭として勤めてきましたが、きー君の障害発覚を機に退職。現在は、パートをしながら療育や子育てに専念しています。
今までに経験したことや学んだことをブログで紹介していきます!
それでは、お読みください!
※この記事でご紹介している就学相談の流れや田中ビネー知能検査の内容は、私たちの自治体での体験をもとにしています。地域によって実施方法や検査内容が異なる場合がありますので、あくまで一例としてご覧ください。
就学相談とは?わかりやすく解説

『就学相談』とは、子どもの小学校入学に「我が子は特別な支援が必要かもしれない…」と感じた保護者が、その子どもにとって最適な教育環境を検討するために受ける相談のことです。
子どもの状態や保護者の意向を踏まえ、専門家(就学相談専門員や心理専門員など)が一緒に進学先を考えていってくれます。
具体的には、通常学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校など…
様々な選択肢の中から、子どもにとって最も適した学びの場を一緒に考えるための相談です。
就学相談って何をするの?流れと準備について
いつ、どうやって案内が来た?
私が就学相談の案内を受けたのは、きー君が通う『子ども発達支援センター』でした。
時期は、年中さんの2月。
もう少しで年長さんというときでした。
子ども発達支援センターで、心理士さんによる療育を受けているとき。
私が元小学校教諭ということもあり、入学前に就学相談を受けるのは以前から知っていたので聞いてみたところ、心理士さんから案内のプリントをいただきました。

自分から聞かなければ、案内はもう少し先になったのかも?
「早めに行動しないと、順番待ちで就学相談がなかなか進まず困ったんだよ~💦」と先輩ママからも聞いていたので、年中さんのうちに聞いてみました!
案内の内容
心理士さんからいただいた案内を見て、やはり就学相談は受けるべき!と思いました。
案内に書かれていた内容はこちら↓
・発達に心配のある子どもの支援の場の選択肢と、支援内容
・特別支援学級設置校一覧
・就学相談の大まかな流れ
特別支援学校以外にも、支援の場はさまざま
| 知的障害特別支援学級 | 知的な発達面で支援が必要な場合 |
| 自閉症・情緒障害特別支援学級 | 情緒や行動面で支援が必要な場合 |
| 自閉症・情緒障害通級指導学級 | 情緒や行動面で支援が必要な場合 |
| 言語障害通級指導教室(ことばの教室) | 言葉の面で支援が必要な場合 |
| 視覚障害特別支援学級 | 視覚に障害があり支援が必要な場合 |
| 視覚障害通級指導教室 | 視覚に障害があり支援が必要な場合 |
| 聴覚障害特別支援学級 | 聴覚に障害があり支援が必要な場合 |
| 聴覚障害通級指導教室 | 聴覚に障害があり支援が必要な場合 |
| 病弱学級 | 病院で入院しているお子さんに支援が必要な場合 |

各学校によって受けられる支援が異なるので、やはり早めの相談が大事!
就学相談の大まかな流れ
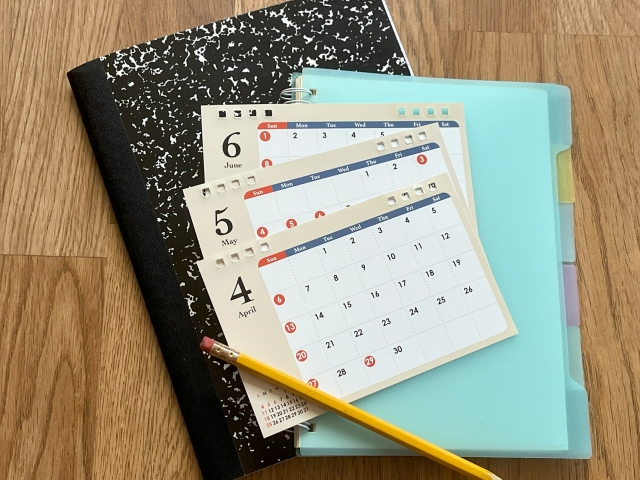
就学相談の大まかな流れは以下の通り↓
①相談受付
②受理面談
③相談開始
④児童観察、発達・知能検査(それぞれ必要に応じて)
⑤学びの場の検討・決定
⑥学びの場に応じた手続き等
相談受付
4月の上旬。
市の教育委員会に電話して面談の予約をしました。
きー君の状況や様子を簡単に説明し、面談(受理面談)の予約を入れました。
面談は4月の中旬に予約できました。
受理面談
4月中旬、市の教育委員会に行って面談をしました。
そこでは、就学相談の申し込み用紙ときー君の成長の記録を記入しました。
所要時間は約1時間30分。
持ち物は、以下の通りでした。
・母子手帳
・マイナンバーカード
・障害者手帳等(あれば)
・子どもの成長の記録が書かれているもの(あれば)
成長の記録は出生時からの今までのことを書いて行きます。
母子手帳以外に記録しているものがあれば、持っていくことをおすすめします。
相談開始
5月上旬。
今度は教育委員会ではなく『教育委員会の分室』(教育委員会の建物内ではなく、きー君の通う子ども発達支援センターと同じ施設内でした)に行き面談をしました。
これから就学相談でお世話になる、担当相談員さんとの面談でした。
子ども1人につき1人、担当相談員さんが付いてくれるようです。
就学相談の流れの確認と、保護者はきー君の進路についてどう考えているか今のところの気持ちを聞かれました。
所要時間は約30分。
発達・知能検査の予約をして帰りました。
児童観察
5月下旬。
『教育委員会の分室』の保育園訪問担当の方が、きー君の保育園に行って様子を観察してくれました。
保育園の担任の先生とも面談をし、普段のきー君の様子を聞き取ってくださったようです。
保護者は行く必要はありませんでした。
発達・知能検査
6月中旬。
『教育委員会の分室』に行って「田中ビネー知能検査V(ファイブ)」を受けてきました。
検査してくれる人は、いつもの担当相談員さんでした。

きー君はいつも通りの様子でしたが、親はやはり緊張💦
当日の流れや様子について紹介します!
※「⑤学びの場の検討・決定」「⑥学びの場に応じた手続き等」については、後日また記事にできたらと思います。
田中ビネー知能検査とは?内容と受け方
田中ビネー知能検査って何?

今回きー君が受けたのは『田中ビネー知能検査V(ファイブ)』というもの。
子どもの「知的な発達の様子」を調べるための検査です。
言葉の理解や記憶力、数の感覚、図形の見方など、さまざまな課題に取り組みます。

お子さんがどんなことが得意で、どこにサポートが必要かを知るヒントになります!
多くの場合、検査員の先生と1対1で遊びや会話をしながら進められていき、おしゃべりやクイズのような雰囲気で行われることが多く、無理に答えさせるようなことはないようです。
検査の結果として出てくるものは3つ。
| 基底年齢 | 全ての問題が合格できる年齢級に”1”を足した年齢 |
| 精神年齢 | 年齢に対してどのくらいの発達の段階にいるか |
| 知能指数(IQ) | 子どもの考える力を同年齢の子どもと比べたときの目安となる数値 |
今後の関わり方や支援の参考にするための目安になります。

検査の前に親として準備するものは特にありませんが、無理に「がんばってね」とプレッシャーをかけないように心掛けました
田中ビネー知能検査とは?発達検査の流れと子の様子【体験談】

検査当日は、持ち物など特になく、指定された時間に『教育委員会の分室』に行きました。
通い慣れた『子ども発達支援センター』と同じ建物内なので、きー君もいつも通りの様子で検査を受けることができました。
検査の流れ
①検査前にトイレへ
②簡単な説明
③検査
④検査終了後、検査結果を聞く日の予約
検査前に一度トイレへ
時間になり、いつもの担当相談員さんが迎えに来てくれました。
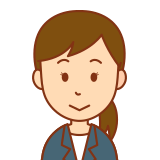
きー君、おはよう!
今日は先生とクイズをするよ
おトイレは大丈夫かな?

おしっこ行ってくるー!!

(しまった、トイレ行かせるの忘れてた💦)
ピューンッとトイレに走っていくきー君。
平静を装いながらも、事前にトイレに行かせることも忘れるほどには緊張していた私。
以前、療育手帳の申請のために(結局取得できませんでしたが…)田中ビネー知能検査を受けに行ったとき、検査途中に先生を引き連れてトイレに向かって行ったきー君を思い出しました。
事前にトイレに行かせておくことをおすすめします。
簡単な説明
検査前に、担当相談員さんからお話が合ったことは以下の3つ↓
・今回受ける検査は『田中ビネー知能検査V(ファイブ)』であること
・所要時間はだいたい45分~1時間
・検査はきー君一人で受けられそうか、保護者も同伴するか
時間は目安で、検査を受ける様子やどこまでできるかによっても変わってくると思います。
一人で受けるかどうかの確認もありました。
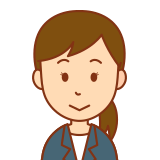
検査はきー君一人で受けられますか?

(以前一人で受けたことがあるし…)
大丈夫だよね!
いってらっしゃい!!

先生、いっぱいクイズやるー?
「ママも一緒に行こうか?」と声を掛けてしまうと絶対に着いてきてと言われそうでしたので、「いってらっしゃい!」と声を掛けました。
検査の様子を見たいという気持ちもありましたが、そこはぐっと我慢。
親のいない空間で、どのくらいきー君が力を発揮できるのか知りたかったからです。
そそくさと先生と手をつないで、検査のお部屋に向かっていくきー君。
私の方がドキドキしながら、きー君の背中を見送りました。
検査
検査中は、私自身は何もすることがありませんでした。
検査室は離れたところにあったため、きー君の声が聞こえてくることもありませんでした。
IQが数値として出ることは何だか怖い気持ちもありましたが、
・IQが出たとして、目の前にいるきー君は今までと変わらないということ
・療育もしっかり受けていて、やれることは十分やっているということ
・IQの数値は一喜一憂するものではなく、適切な支援を受けるための判断材料であるということ
以上の3つを頭の中で自分に言い聞かせながら、きー君が無事に帰ってくるのを待ちました。
検査終了後
50分くらいして、担当相談員さんときー君が戻ってきました。
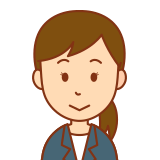
きー君、頑張っていましたよ
後から疲れが出てくると思うので、ゆっくり休んでくださいね
ホッとしたのも束の間、担当相談員さんからの提案に思わず息をのみました。
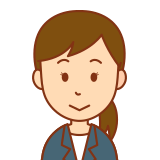
やはり、 WISC(ウィスク)も受けた方がよさそうですね
きー君の得意不得意をもう少し詳しく調べたいとのことで、夏休み中にWISC(ウィスク)を受けることに…
こちらもIQが出る検査なので緊張しますが、きー君の適切な進路を考えるためにはやるしかありません。
とりあえず、今回の田中ビネー知能検査の結果が聞けるのは1週間後ということで、予約だけして帰宅しました。
就学相談を受けて感じたことと、これからの気持ち
不安もあったけれど、得られた安心
就学相談について、最初は不安もあったけれど早めに動いてよかったと思っています。
教育委員会の方々も、今回お世話になっている担当相談員さんも、一生懸命にきー君について知ろうと取り組んでくださっているのが伝わり、安心して相談することができています。
就学相談でこれから関わるであろう方々のご意見、検査の数値、そして保護者の考え。
それらをすり合わせて、きー君が楽しくも学びある学校生活を送るための進路を考えていきたいです。

じっくり進路を考えるためにも、早めの相談をおすすめします!
これから就学相談を受けるママやパパへ

初めての就学相談。
「何を聞かれるんだろう」
「ちゃんと伝えられるかな」
「この子に合った進路ってなんだろう」
そんなふうに、私もずっと不安で、胸の奥がモヤモヤしていました。
きー君にまだ診断名が付いていなかった頃。
きー君の様子について説明しなければならない場で、涙が止まらずにうまく話せなかったときのことを思い出しました。
あの時みたいに、また取り乱してしまったらどうしよう…

でも、就学相談を進めていて、ふと気がつきました。
「私、ちゃんとこの子のことを話せてる」
「一緒に考えてくれる人がいるって、こんなに心強いんだ」と。
就学相談は、「決めつける場所」ではなくて、「一緒に考える場所」だと私は考えています。
あなたの気持ちも、お子さんの個性も特性も、まるごと受けとめてくれる人たちがきっといる。
中には、経験豊富が故に障害名や知能指数で進路を決めようとする人がいるかもしれません。
ですが、その時は、
「この子にはこういう個性があって、このように学校生活を過ごしてほしい」
と素直に親の気持ちを言葉にして、協力してくださる方々と一緒に進路を決めていけたらなと思っています。
不安な気持ちのままで大丈夫。
そのままのあなたで、どうか一歩、勇気を出してみてください。
その一歩が、きっと未来につながっていきます。

わからないことばかりで不安💦
だけど、こうやって情報を共有して、一緒に頑張っていきましょう😊
田中ビネー知能検査の結果や、WISC(ウィスク)についても今後書いて行けたらと思っています
それでは、また!
※地域や自治体によって就学相談の内容・検査方法は異なる場合があります。この記事は私たちの体験をもとにした記録です。
【関連記事】
▶田中ビネー知能検査でIQ85|自閉スペクトラム症の息子の就学先をどう選ぶ?
▶就学相談でWISC-Ⅳを受けた結果|IQ85→97だった自閉症の息子と進路の決断
▶小学校見学についてもまた記事にします(準備中)