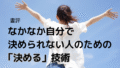「IQ85」
その数値を、私と夫は静かな部屋で聞きました。
私は、元小学校教諭として15年間たくさんの子どもたちと関わってきました。
知能指数による子どもの現状や、必要な支援について考える。
それは経験したことのある仕事のひとつでした。
けれど今回は違いました。
目の前にあるのは、“我が子”の結果。
教育的な視点と母親としての気持ちが、頭の中でせめぎ合いました。
この記事では、息子・きー君が田中ビネー知能検査を受けたあと、「IQ85」という結果を伝えられたときのこと。
そして、元教員である私が、親としてどのようにこの数値と向き合っているのか――
今まさに「わが家の進学先」を検討中の現状とともに、率直にお伝えします。

就学相談ってどんなことをするんだろう?
知能検査の結果から、どのように進学先を考えていったらいいのだろう…
このようなお悩みに対して、この記事では以下のことがわかります。
・IQ85という数値を、教員と親の両視点からどのように受け止めたか
・就学相談は“決定の場”ではなく“対話の場”であるという考え方
・進学に向けた検討状況と、これからのステップ(WISC検査や学校見学など)

自閉スペクトラム症の6歳の息子(きー君)と、今のところ定型発達であろう3歳の娘(あーちゃん)を育てています!
障害児育児は6年目。15年間小学校教諭として勤めてきましたが、きー君の障害発覚を機に退職。現在は、パートをしながら療育や子育てに専念しています。
今までに経験したことや学んだことをブログで紹介していきます!

きー君のパパです!
今回はぼくも参加します!
同じように悩み、不安を抱えるご家族の方へ。
まだ「途中」の私たちの話が、少しでもヒントや励みになれば幸いです。
それでは、お読みください!
【補足】検査の種類や支援の選択肢の出され方も自治体によって異なります。本記事では、わが家の体験をもとにご紹介しています。
元小学校教諭の私が直面した「IQ85」:親として向き合う瞬間
子ども発達センターで療育を受けているとき、進学先について相談したところ案内された『就学相談』。
きー君の知的な発達の具合を把握するために「田中ビネー知能検査V(ファイブ)」を受け、結果を聞く日になりました。

検査から結果を聞くまでは1週間。
長いようで、あっという間の1週間でした。
担当相談員から告げられた「IQ85」

その日、きー君は保育園へ。
夫も何かを察したのか、仕事を中抜けして、私と一緒に来てくれました。
夫婦二人で就学相談の結果を聞きに行くことに。
以前検査が行われた階は、他の親子連れの賑やかな声が聞こえていました。
でも、結果を告げられることになった部屋は、全く別の階。
廊下には私たち以外誰も見当たらず、担当相談員さんと夫、そして私の3人の靴の音だけが、やけに大きく響いていました。
その音を聞くたび、私の肩は徐々に力が入っていくのを感じました。
案内された部屋は、とても静かでした。
何も置かれていないテーブルとパイプ椅子、殺風景な白い壁。
少しひんやりとした空気が張り詰める中、私は掛けられる言葉を待っていました。
私の目の前には、分厚いファイルと、手元の資料を見つめる担当相談員さん。
そして、結果が書かれたたった1枚のプリントが、そっと差し出されました。
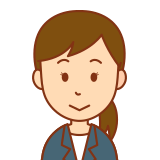
きー君のIQは、85という結果でした。
そう聞いた瞬間、不思議な感覚に包まれました。
教員時代に、何度も触れてきたはずの“数値”。
子どものIQ。
私にとっては、聞き慣れた言葉だったはずなのに。
内心、冷静ではいられませんでした。
頭では理解しているのに、胸の奥がぎゅっと締め付けられて、言葉が出なくなってしまったんです。
「そうなんですね」と、ようやく絞り出した声は、自分のものではないかと思うほど小さくて。
返事をするので精一杯でした。
「親」として受け止めた感情の揺れ
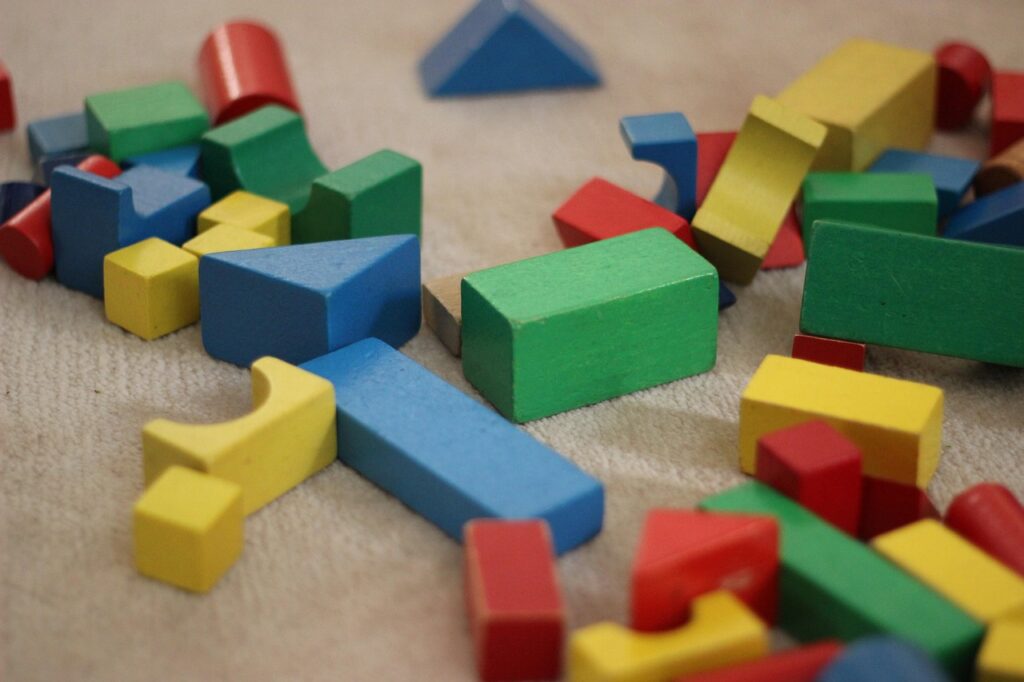
教員として、その子どもに必要な支援について、知能指数を参考に考え実行してきた経験があります。
数値が、子どもの特性や支援の方向性を考える上で、一つの大切な情報になることも知っていました。
保護者の方から子どもの知能指数について相談を受けたときには、冷静に、客観的に数値と向き合ってきた経験もあります。
けれど、今回目の前に突きつけられた「IQ85」という数字に、心が大きく揺さぶられたのです。
私の息子、きー君の“今”を表す数字。
その瞬間、私の頭の中で、これまで培ってきた教員の知識と、親としての感情が激しくぶつかり合いました。
頭では理解できるはずのことが、感情ではなかなか受け止められない。
自分の子どもであるという事実が、こんなにも私を揺さぶるのかと、戸惑いました。
検査結果の具体的な数値と、担当相談員からの提案
きー君の検査の結果から、担当相談員さんから進学先の提案がありました。
まずは、きー君の結果をもう少し詳しく紹介します。
きー君の「田中ビネー知能検査V」の具体的数値
| 生活年齢 | 6歳1ヶ月 |
| 基底年齢 | 3歳(2歳級+1) |
| 精神年齢 | 5歳2ヶ月 |
| 知能指数(IQ) | 85 |

IQ85って、どの程度の知的水準なの?

IQ85は平均域の下
あと1点低ければ境界知能域に入るよ
生活年齢は、実際の今の年齢。
基底年齢とは、全ての問題が合格できる年齢級に”1″を足した年齢であり、きー君は2歳級の問題までは全問正解できたということです。
そこから算出された精神年齢は5歳2ヶ月で、生活年齢と比べると11ヶ月の発達の遅れがあることがわかります。
さらに、田中ビネー知能検査のIQは高めに出るということもあり(4~6歳の平均はIQ118)、同学年の定型発達のお子さんについていくのはかなり苦労するだろうな…と感じました。

担当相談員から告げられた、進学先の提案
担当相談員さんからは、『自閉症・情緒障害特別支援級(情緒級)』を勧められました。
『情緒級』は、近所の小学校の特別支援学級に所属します。

情緒級?
通常級や知的級とはどうちがうの?

通常級は、特別な支援を必要としない、または軽度の支援があれば学校生活を送れる児童生徒が在籍する一般的な学級のこと。
情緒級は、情緒や行動面で支援が必要な場合に通うよ。
通常級で学習できそうな教科や時間(朝の会・給食の時間など)があれば、情緒級の担任や支援さん付き添いの下、通常級で過ごすこともできるんだ。
知的級は、学習面や日常生活で特別な支援が必要なお子さんが、それぞれのペースで学習を進めることができ、生活に即した実践的な学習を行う学級ことをいうよ。
担当相談員さんによる、情緒級がきー君に合いそうだという根拠は以下の通り。
・発達の凸凹が大きそうであり、全体的な発達のゆっくりさもある
・検査時のきー君の多動さから、誰かがそばについてこまめに声を掛ける等の支援が必要
・基本的生活動作がある程度できることやIQ85という数値から、『知的障害特別支援学級(知的級)』より情緒級が合いそう
きー君は、得意な問題は6歳級の問題を解くことができたが、苦手な問題は3歳級の問題で間違えたそうです。
検査中も、説明の途中で気になるものがあると我慢できなくなったり、制止の声があっても離席してしまうことがあったりもしたそうで、集団での学習の難しさもかなりありそうです。
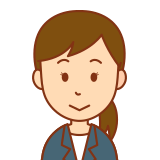
情緒級をおすすめします
もしくは通常級からスタートするということも…
『通常級』という言葉も担当相談員さんからちらりと出てはきましたが、「それはないな」というのが私の率直な意見です。
長くなるのでここでは詳しくは割愛しますが、これまでの教員の経験からそう思いました。
きー君の様子から考えるに、学習面において、1年生は通常級でも何とか食らいついていける可能性もあります。
それでも家庭での学習のサポートがかなり必要。
2・3年生になって学習が抽象的なものになってくると、相当本人が苦労するようになることが予想されます。
さらに、多動という特性が入ってくると、授業中に小まめな声掛けなどの支援が必要になってくるでしょう。
離席も考えられます。
十分なサポートをすることは、通常級の担任一人ではかなり難しいです。
学習面だけでなく、友達とのコミュニケーションも、小学校に上がるとより複雑になってきます。
なので、現時点では1年生の最初から『情緒級』というのが、今のところの私の考えです。

通常級からスタートしてみるっていうのも、アリだと思うけど…

正直、無理をして苦しんでいるお子さんや保護者を何人も見てきたんだ。
障害の程度によっては、うまくいくケースもあるのかもしれないけど…
そういうお子さんを、担任一人では通常級で十分サポートできなかった経験があるんだ。
通常級に在籍してしまうと、その子専属のサポートの先生を付けることが難しい学校の現状もあって、最初から情緒級がいいかなと思っているよ。
支援のかたちをどう選ぶか:今後の予定と、わが家のこれから
おおむね進学先は『情緒級』という方向で考えていますが、現時点で未確定です。
今後、就学相談でやることが決まっているのは以下の2つ↓
・WISC検査の実施
・小学校見学
WISC検査で、発達の凸凹をより詳しく把握していきます。
そして、きー君が通うであろう近所の小学校の『情緒級』を見学して、進学先の方向性をしぼっていく予定です。
こちらの様子についても、今後記事にしていけたらと思っています。
元教員だからこそ伝えたい:就学相談は「判断」ではなく「対話」

今までは、教員としての立場でしか触れてこなかった就学相談。
「その子の最適な学びの場を探すプロセス」として、ひたすらに前向きな気持ちで捉えていました。
そして現在、親の立場になり、今は痛いほどわかります。
「就学相談=能力をジャッジする場」のように感じてしまうということ。
次は何を言われるのかな…?という不安な気持ち。
就学相談を進める一つ一つが、現実を突きつけられて悲しくもなります。
でも、数値はあくまでひとつの判断材料であり、母親の私が見ている“きー君”の姿も進路を考える上で重要になってきます。
就学相談で関わる方々は、
「判定する人」ではなく、子どもの未来を一緒に考えていく「仲間」
言われるがままに決めていくのもちがうし、母親の希望を貫き通すのもちがう。
『学校が我が子にとって過ごしやすく、能力を伸ばしていける場』となるように、関わる方々としっかりと対話しながら決定していきたいです。

迷ってもいい、不安でも大丈夫!
一緒に考えてくれる人は必ずいます。
わが子のためにできること:不安と希望のあいだで

進学先は、まだ決まっていません。
田中ビネー知能検査の結果を受け取り、「そうか、IQ85か」と思った瞬間、頭では理解していても、心の中には小さな波が立ちました。
そして今、WISC検査を控え、小学校見学を予定している段階です。
正直、まだ迷っています。

この子にとって、一番安心できる場所はどこだろう?
どんなサポートがあれば、伸びていけるんだろう?
親として考えれば考えるほど、「これが正解」という答えは見つかりません。
でも、だからこそ今、この途中経過を綴りたいと思いました。
まだ決まっていない。
でも、確実に前に進んでいる。
わからないからこそ、動いて、話して、知ろうとしている。
それはきっと、私にできる「わが子のための行動」なんだと思っています。
最終的な進路は、検査結果や専門家の意見、そして家族としての想いを丁寧に重ねながら決めていく予定です。
そして何よりも大切にしたいのは、「この子が笑顔でいられる毎日をどうつくるか」という視点です。
迷っている今だからこそ伝えられることがある。
この記事が、同じように悩みながら歩いている誰かの小さな支えになれば嬉しいです。
一緒に頑張っていきましょう。
それでは、また!
※この記事で紹介している就学相談の体験は、あくまでわが家の地域での事例です。自治体や地域により制度や対応は異なる場合がありますので、参考のひとつとしてください。
【関連記事】
▶【体験談】就学相談と田中ビネー知能検査の流れ|自閉症の息子が受けた様子と親の本音
▶就学相談でWISC-Ⅳを受けた結果|IQ85→97だった自閉症の息子と進路の決断
▶学校見学についても、また記事にします(準備中)